コピーコンテンツが与える影響。どう対策する?
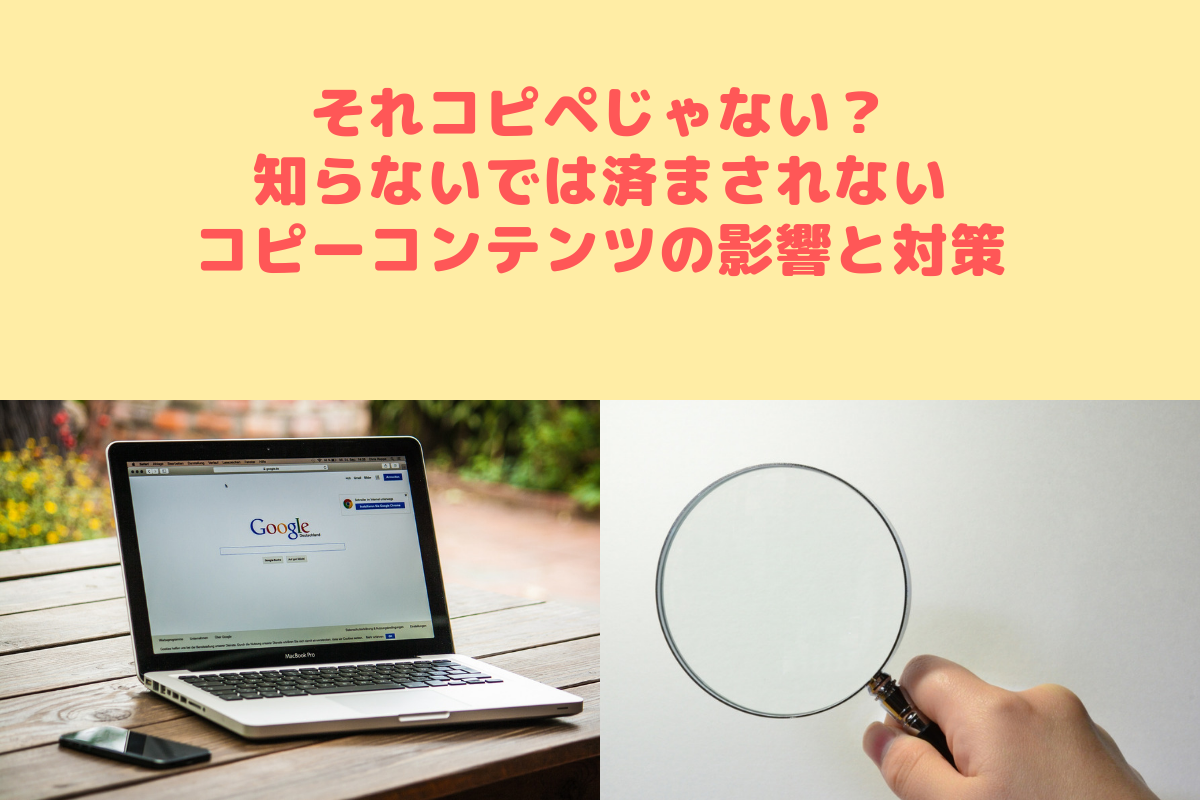
ネットサーフィンをしている時、お店やブログのサイト内の文章が「どれも似ているな」と感じた経験はありませんか?
その似ている文章には、元になっているものが必ずあります。
そして、それを誰かが無断で自分のものにしているケースが多くあります。
これを「コピーコンテンツ」といいます。
コピーコンテンツは、すべてがNGという訳ではありません。
しかし、コピーコンテンツはコピーをした側や、された側にも様々な影響を与える恐れがあります。
健全なサイトを運営するためにも、コピーコンテンツを防ぐことは、とても大切です。
今回は、コピーコンテンツとは何かを分析し、SEOに与える影響や対処法を皆さまにお伝えします。
「自分のサイトがコピーコンテンツかどうか不安」「コピーコンテンツが与える影響を知りたい」などをお考えの方は、記事を是非ご覧ください。
Contents
コピーコンテンツとは?

まず、コピーコンテンツとは何かをご説明します。
コピーコンテンツとは「他のサイトのページにある、文章や画像をコピーすること」や「コピーしたものをオリジナルのように見せること」などのことを指します。
他のサイトからコピーしたにも関わらず、その文章をまるで自分が書いたかのように装った状態であり、著作権の侵害行為である可能性があります。
そのような行為に対し、Googleに代表される検索エンジンは、コピーコンテンツをスパム行為と捉えており、厳しく対応しているのです。
また、複数のサイトを用意している場合、同じ文章を使い回すこともコピーコンテンツに該当するケースがあるため、運用には細心の注意が必要です。
コピーコンテンツがSEOに与える影響
コピーコンテンツだと検索エンジンが判断すると、ペナルティーとして様々な問題が起きる可能性があります。
・検索順位が下がる
グーグルの検索品質チームで活躍していたマット・カッツ氏は「インターネットの25~30%はコピーコンテンツだ」と発言しています。
しかし、コピーコンテンツの場合は、検索エンジンからの評価が下がる傾向にあるため、検索順位に影響が出るかもしれません。
すぐに評価と検索順位が下がることはありませんが、コピーコンテンツを放置していれば、後々にペナルティーを受ける可能性はあります。
・検索結果に表示されない
コピーコンテンツが増えると「検索時に表示される結果が同じものばかり」という事態を引き起こす原因になります。
検索エンジンは、サイトの独自性を重視しており、できるだけ同じものを表示しないための仕組みがあります。
それにより、コピーコンテンツばかりで構成されているサイトは、どれだけ更新しても検索結果に表示されにくくなっているのです。
コピーコンテンツは本当にダメなの?
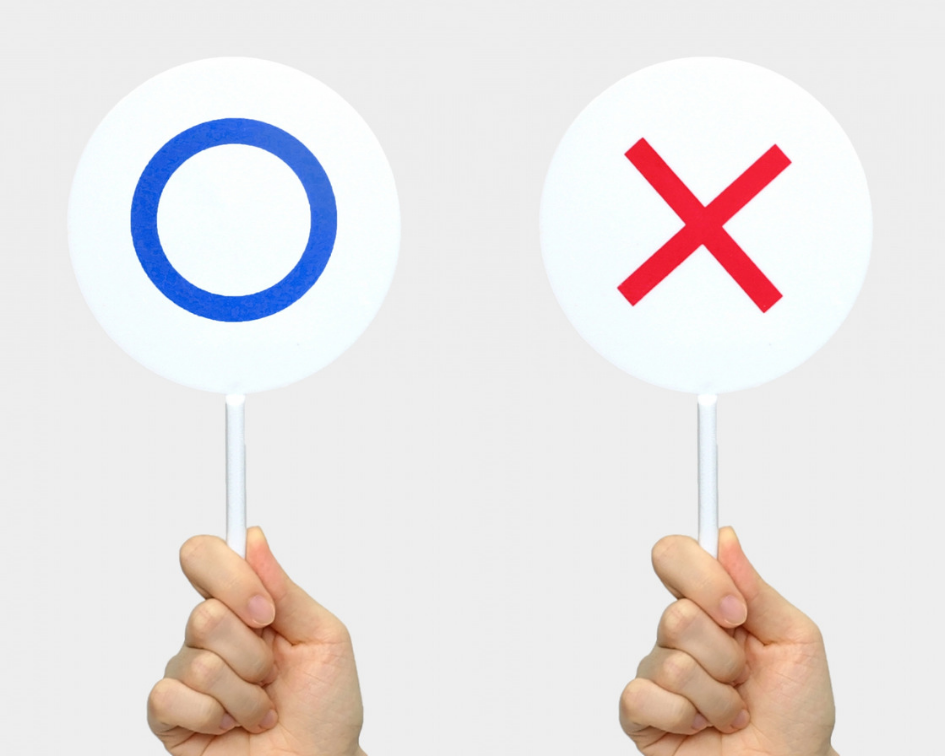
結論から言うと「コピーコンテンツだからダメ!」というわけではありません。許されるコピーコンテンツもあります。
コピーコンテンツだとしても許されるケースをご紹介します。
・引用タグを使用し、引用元も明記している
引用タグとは、検索エンジンに「この中身は引用です」と伝える役割を持つタグです。
著作権侵害を避けるためにも、引用タグを必ず使用し、引用元を書くことを忘れないようにしましょう。
しかし、引用ばかりしているとオリジナルとしての評価が下がり、コピーコンテンツ扱いになる恐れがあるので、注意が必要です。
・リライトをしている
同じ情報を単にコピーするのではなく、文章の構成や言い回しを変える「リライト」をおこない、コピーコンテンツという判断を避けることもできます。
リライトをきちんとできていれば、参考にしたコンテンツがあるとしても、完成した文章はオリジナルと判断されるようです。
上記のルールを守っていれば、コピーコンテンツとされる可能性は低くなります。\
しかし、節度というものを守らなければいけません。
ルールを守っているとはいえ、そのページ全体が引用された文章ばかりであれば、それはオリジナルと言えず、コピーコンテンツと判断されてしまいます。
バランスを考えた文章作成を心がけたいものです。
コピーされた場合はどうしたら良い?
もし、自分もしくは自社サイト内のコンテンツが、別サイトでコピーされていた場合、どのような対策をすれば良いかをご紹介します。
サイト管理者やコピーした企業に対してクレームを入れる
あまりにも内容が似ていて、コピー率も非常に高い場合は、コピーしたと思われるサイトの管理者や企業に「削除依頼」をおこないましょう。
依頼に従ってくれれば良いのですが、対応してくれない場合もあります。
グーグルに著作権侵害の申し立てを直接おこなう
著作権侵害の申し立てを、グーグルに直接おこなう方法があります。
それが、デジタルミレニアム著作権法(Digital Millennium Copyright Act)の略称である「DMCA申請」です。
この方法で申請がおこなわれると、グーグルは著作権を侵害していると思われるコピー先のコンテンツを慎重に審査します。
そして、コピーコンテンツだと判断した場合、そのコンテンツは検索結果から排除されるのです。
サイト管理者や企業に削除依頼をしたのに、対応してくれない場合の最終手段といえます。
まとめ
コピーコンテンツだと判断された場合、厳しい対応が科されることをご理解いただけたと思います。
コンテンツにオリジナリティーがあることは理想的ですが、コピーコンテンツが生まれてしまう場合もあります。
コピーコンテンツを防ぐためには、引用のルール守り、リライトをおこなうことで、オリジナルに近づける努力をしましょう。
そして、SEO対策やコピーされた時の対策を知っておくことで、万が一の事態に備えることも大切です。
これまでに、全国で2000件を超える制作・集客の経験を生かし、医療分野の最新情報と実践的な経営戦略をご提供します。
ミッションは、医療業界のプロフェッショナルに、専門性と実績に基づく知識と最新情報を届けること。医療の専門家が直面する挑戦に対応し続け、業界全体の発展をサポートします。







